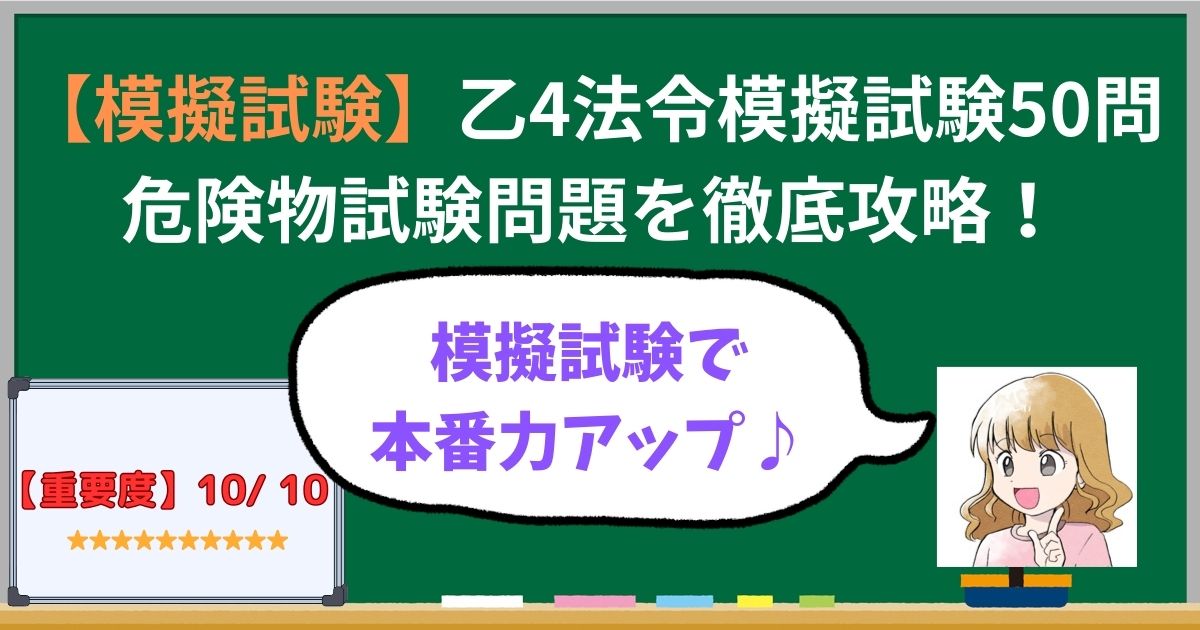「模擬試験を解いてもなぜか点が伸びない…」「覚えたはずなのに、本番形式になると焦ってしまう…」
そんな不安を感じている方へ。
この講座では、乙4法令模擬試験に特化した実践型トレーニング問題集をご用意しました。
危険物試験問題の中でもとくに出題率の高いテーマをもとに、ひっかけや複合問題を含んだ全50問のオリジナル問題で、試験直前の総仕上げができます。
【この講座の重要度】 10 / 10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
💡最重要:試験によく出る&合格に直結する知識。必ず押さえておこう!
この講座でできること
- 無料で独学OK! 乙4実践問題の形式に慣れ、本番で慌てない力を身につける
- 「指定数量」「施設分類」「届出の要否」など、よく出る論点を効率よくチェック
- 条文の理解から応用力まで、読解力と判断力を磨く模擬演習が可能
この講座を通じて、苦手な法令分野を克服し、試験当日は「見たことある!」と感じられる問題が増えていきます。
模擬試験で実力を確かめて、本番に自信をもって臨める状態を目指しましょう。

よーし、ついに模擬試験か! これって本番と同じ形式なんだよね?
そうだよ。特にこの50問は、乙4の法令分野でよく出るテーマをしっかり押さえてあるの。届出・許可の違いや施設の分類、苦手な人多いからね


あー…1倍超えたら全部許可って覚えたけど、それでいける?
それ、半分合ってて半分アウト(笑)施設の種類によって届出で済むこともあるよ。ひっかけ問題で狙われやすいから注意してね。では、始めてみよう!

※この問題集は、過去問の出題傾向に基づいて作成したオリジナル問題です。
危険物取扱者法の基本|資格の目的と範囲を問う
危険物取扱者試験(乙種第4類)では、法令分野の出題が全体の3分の1以上を占める重要なパートです。
この章では、試験で問われやすい「危険物取扱者法の目的」「乙4で扱える危険物の範囲」「免状の違い」など、資格制度の基礎を整理していきます。
法令の理解が曖昧なままでは得点が安定せず、応用問題にも対応しづらくなります。
まずは、基礎を丁寧に確認するところから始めましょう。
この章の目次
📌 問題1:【基礎確認】危険物取扱者の制度目的とは?
危険物取扱者の制度が設けられている目的として、正しいものはどれでしょうか?
1️⃣ 危険物の価格を適正に維持するため
2️⃣ 危険物の輸出入を自由化するため
3️⃣ 危険物による火災・爆発などの災害を防ぎ、人命や財産を守るため
4️⃣ 危険物を扱う企業の経営を保護するため
📌 問題2:【基礎確認】乙種第4類で取り扱える危険物は?
次のうち、「乙種第4類」資格で取り扱うことができる危険物の種類として正しいものはどれですか?
1️⃣ 火薬類
2️⃣ 酸化性液体
3️⃣ 引火性液体
4️⃣ 放射性物質
📌 問題3:【過去問レベル】乙4と他の種別との違いは?
次のうち、「乙種第4類」と「甲種」「丙種」との主な違いとして正しいものはどれですか?
1️⃣ 乙4だけは保安監督者になれない
2️⃣ 甲種はすべての危険物を扱えるが、乙種はそれぞれの類ごとに資格が必要
3️⃣ 丙種は乙4よりも広い範囲の危険物を取り扱える
4️⃣ 乙4だけが5年ごとの更新義務がある
📌 問題4:【基礎確認】免状の再交付が必要な場合は?
次のうち、危険物取扱者免状の「再交付」が必要になる状況として正しいものはどれですか?
1️⃣ 試験に合格したが得点が低かった場合
2️⃣ 勤務先の企業を異動した場合
3️⃣ 免状を紛失したり、破損して読めなくなった場合
4️⃣ 毎年の有効期限が来た場合
📌 問題5:【過去問レベル】乙4試験に出題される法令の範囲は?
乙種第4類の試験において、法令問題の出題範囲に含まれるものとして正しいのはどれですか?
1️⃣ 消防法と高圧ガス保安法
2️⃣ 消防法およびその施行令・施行規則
3️⃣ 労働安全衛生法のみ
4️⃣ 建築基準法と消防法の一部
指定数量と計算問題|試験頻出テーマを攻略
危険物取扱者(乙4)の試験では、「指定数量」の理解が得点を左右する重要な項目です。
とくに計算問題は、出題パターンに慣れておくことでミスを防げるようになります。
このパートでは、危険物試験問題でもよく問われる「乙4実践問題」を中心に、合計10問を出題しています。
基本用語の確認から、合算や倍数計算の応用まで、しっかり対策していきましょう。
この章の目次
- 📌 問題6:【基礎確認】「指定数量」とは何を指す?
- 📌 問題7:【過去問レベル】ガソリン200L保管時の手続きは?
- 📌 問題8:【過去問レベル】指定数量1.2倍で必要な手続きは?
- 📌 問題9:【応用・実戦】ガソリン2,000L保管時の区分は?
- 📌 問題10:【過去問レベル】指定数量の倍数計算で誤っているものは?
- 📌 問題11:【過去問レベル】危険物の合算計算で正しいのはどれ?
- 📌 問題12:【応用・実戦】倍数計算の注意点として正しいものは?
- 📌 問題13:【過去問レベル】指定数量と施設設置基準の関係性は?
- 📌 問題14:【応用・実戦】指定数量の合算と手続き判断
- 📌 問題15:【応用・実戦】倍数超過による罰則の適用条件は?
📌 問題6:【基礎確認】「指定数量」とは何を指す?
危険物取扱において使われる「指定数量」という用語の意味として、最も適切なものはどれですか?
1️⃣ 危険物の最小保管量を示す基準
2️⃣ 届出が不要な最大の数量
3️⃣ 危険物の種類ごとに法律で定められた基準量
4️⃣ 危険物の販売価格を決定するための数量基準
📌 問題7:【過去問レベル】ガソリン200L保管時の手続きは?
事業所でガソリンをちょうど200L(=指定数量1倍)保管する予定です。このとき必要な手続きはどれでしょうか?
1️⃣ 特に届出は必要ない
2️⃣ 管轄の消防署へ届出が必要
3️⃣ 許可申請が必要になる
4️⃣ 消防法の対象外となる
📌 問題8:【過去問レベル】指定数量1.2倍で必要な手続きは?
ある工場に設置された屋内貯蔵所で、引火性液体を指定数量の1.2倍保管する予定です。 この場合、通常どのような手続きが必要となるでしょうか?
1️⃣ 手続きは不要
2️⃣ 届出だけでよい
3️⃣ 許可申請が必要になる可能性が高い
4️⃣ 市町村長への報告だけ行えばよい
📌 問題9:【応用・実戦】ガソリン2,000L保管時の区分は?
屋内タンク貯蔵所において、ガソリンを2,000L保管する場合、必要となる手続きはどれでしょうか? (※ガソリンの指定数量=200L)
1️⃣ 届出だけで保管できる
2️⃣ 許可申請が必要(第2種貯蔵所に該当)
3️⃣ 消防署の立入検査のみで対応可能
4️⃣ 特に申請は不要、任意管理でOK
📌 問題10:【過去問レベル】指定数量の倍数計算で誤っているものは?
次のうち、「指定数量に基づく倍数計算」に関する説明として誤っているものはどれでしょうか?
1️⃣ 危険物ごとに定められた指定数量を基準とする
2️⃣ 実際の数量を指定数量で割って倍数を求める
3️⃣ 類が異なっていても、危険性が似ていれば合算される場合がある
4️⃣ 同じ類であれば、性質に関係なく必ず合算する
📌 問題11:【過去問レベル】危険物の合算計算で正しいのはどれ?
次のうち、危険物の合算計算に関する説明として正しいものはどれですか?
1️⃣ 第4類の危険物は、それぞれ個別に判断し、合算の必要はない
2️⃣ 危険物はすべての類を通じて合算対象となる
3️⃣ 同じ類に属し、かつ危険性が類似する危険物は合算して判断する
4️⃣ 合算計算が必要なのは、第1類と第6類の危険物に限られる
📌 問題12:【応用・実戦】倍数計算の注意点として正しいものは?
次の説明のうち、「倍数計算」に関する注意点として最も適切なものはどれですか?
1️⃣ 計算結果の小数点以下はすべて切り捨てて処理する
2️⃣ 合計の倍数が1未満でも、施設の条件によっては許可が必要となる
3️⃣ 危険物の保管量が少なければ、倍数計算は行わなくてもよい
4️⃣ 一度計算すれば、以後は変更があっても再計算は不要である
📌 問題13:【過去問レベル】指定数量と施設設置基準の関係性は?
危険物の保管量と施設の設置基準について、正しく説明しているものはどれですか?
1️⃣ どれだけ保管しても、施設の種類は自由に選べる
2️⃣ 指定数量を1倍超えると、自動的に屋外タンク貯蔵所としなければならない
3️⃣ 指定数量の「倍数」に応じて、設置できる施設の区分が定められている
4️⃣ 保管量が少ないほど、設置基準は逆に厳格になる
📌 問題14:【応用・実戦】指定数量の合算と手続き判断
ある事業所で、以下の危険物を屋内貯蔵所に保管しようとしています。このとき、必要となる手続きとして最も適切なものはどれですか?
・ガソリン:300L(指定数量200L)
・灯油:800L(指定数量1,000L)
※いずれも第4類引火性液体とする
1️⃣ 特に手続きは不要
2️⃣ 届出を行えば保管可能
3️⃣ 保管には許可申請が必要となる
4️⃣ この組み合わせでは保管自体ができない
📌 問題15:【応用・実戦】倍数超過による罰則の適用条件は?
次のうち、「指定数量を超えて危険物を無許可で保管した場合」に該当する内容として正しいものはどれですか?
1️⃣ 保管後3日以内に届け出れば、罰則は適用されない
2️⃣ 初回なら行政指導のみで済み、罰則は科されない
3️⃣ 消防法により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となることがある
4️⃣ 実際に火災などの被害が出ていなければ、処罰されることはない
危険物の保管・運搬|出題率の高い重要テーマ
危険物取扱者(乙種第4類)の法令分野では、「保管・運搬」に関する出題が毎年安定して見られます。
とくに、実務にも深く関わる内容だけに、具体的な規定や基準をしっかりと理解しておくことが得点につながります。
ここでは、実際の乙4法令模擬試験や過去の危険物試験問題を参考に、重要ポイントを5問に凝縮しました。
「運搬時の表示義務」や「屋内貯蔵所の条件」「容器の取り扱い」など、試験でも問われやすい論点を丁寧に確認していきます。
この章の目次
📌 問題16:【過去問レベル】運搬時に必要な表示と書類は?
危険物を車両で運搬する際、以下のうち適切な対応として正しいものはどれでしょうか?
1️⃣ 危険物の品名リストを車内に常備すればよい
2️⃣ 車両の前後に「火気厳禁」などの表示を掲示する
3️⃣ 危険物取扱者の免状を提示すれば他の準備は不要
4️⃣ 普通貨物扱いにすれば特別な表示は必要ない
📌 問題17:【基礎確認】屋内貯蔵所における保管構造の基準とは?
屋内貯蔵所に関する基準として、適切なものを次の中から選んでください。
1️⃣ 自然換気のみが認められ、機械換気は禁止されている
2️⃣ 扉や出入口は常時密閉されていなければならない
3️⃣ 床面は不浸透性かつ、漏えい時に排水できる構造が求められる
4️⃣ 窓を多く設けることで安全性が高まるとされている
📌 問題18:【過去問レベル】危険物の運搬容器に関する誤りは?
次のうち、危険物の運搬容器に関する説明として誤っているものはどれですか?
1️⃣ 漏れを防ぐために密閉構造が求められる
2️⃣ 容器には危険物の種類や内容量を明記する
3️⃣ プラスチック容器であれば構造規定は適用されない
4️⃣ 損傷や腐食のある容器は使用できない
📌 問題19:【応用・実戦】屋内タンクでのガソリン保管上限は?
一般的な構造の屋内タンク貯蔵所における、ガソリンの最大保管量として正しいものを選んでください。
1️⃣ 600L
2️⃣ 2,000L
3️⃣ 5,000L
4️⃣ 10,000L
📌 問題20:【過去問レベル】危険物運搬に関する消防法の条文は?
次のうち、危険物の運搬に関する規定が記載されている消防法の条文はどれでしょうか?
1️⃣ 第8条
2️⃣ 第12条
3️⃣ 第16条
4️⃣ 第21条
危険物施設の分類|製造所・貯蔵所・取扱所の違いを押さえる
乙4試験の法令分野では、危険物を取り扱う施設の分類に関する出題が頻出です。
特に「製造所・貯蔵所・取扱所」の違いは混同しやすいため、ここでしっかりと整理しておくことが大切です。
実際の試験でも、施設の定義と設置基準を複合的に問う出題が増えている傾向があります。
この章の目次
📌 問題21【基礎確認】製造所の主な特徴とは?
次のうち、消防法における「製造所」として正しく定義されている施設はどれでしょう?
1️⃣ 危険物を保管する倉庫
2️⃣ 危険物を製造・精製・調合する施設
3️⃣ 危険物を運搬するための中継拠点
4️⃣ 危険物を一般に販売する店舗
📌 問題22【基礎確認】貯蔵所の定義とは?
次のうち、「危険物の貯蔵所」として正しく説明されているのはどれでしょう?
1️⃣ 危険物の製造を行う施設
2️⃣ 危険物の販売や給油を行う施設
3️⃣ 危険物を一時的に仮置きするスペース
4️⃣ 危険物を一定量以上、安全に保管するための施設
📌 問題23【過去問レベル】取扱所で行われる作業は?
次のうち、取扱所で主に行われる作業として正しいものはどれでしょう?
1️⃣ 危険物を化学的に精製する作業
2️⃣ 危険物を販売したり小分けしたりする作業
3️⃣ 危険物を長期保管するための設備
4️⃣ 危険物を廃棄・燃焼処理する作業
📌 問題24【応用・実戦】仮設施設とはどんなもの?
次のうち、「仮設施設」として分類される可能性があるのはどれでしょう?
1️⃣ 地下タンク付きの常設給油所
2️⃣ 祭り会場に期間限定で設置された簡易給油設備
3️⃣ 製造機器を備えた恒久的な工場設備
4️⃣ 危険物を一切使用しないイベントブース
📌 問題25【過去問レベル】屋外タンクの分類として正しいものは?
屋外に設置された危険物用タンクを含む施設は、消防法上どの分類にあたるでしょう?
1️⃣ 屋外タンク貯蔵所
2️⃣ 製造所
3️⃣ 仮設施設
4️⃣ 地下タンク貯蔵所
📌 問題26【応用・実戦】取扱所の設置基準に関する判断
取扱所を設置する際の基準として、次のうち正しいものはどれでしょう?
1️⃣ すべての取扱所は例外なく許可が必要である
2️⃣ 危険物の量にかかわらず、必ず届出が必要
3️⃣ 指定数量を超える危険物を取り扱う場合には、許可が必要になる
4️⃣ 地上に設置してはならず、地下設置が原則とされている
📌 問題27【過去問レベル】施設と指定数量の関係として正しいのは?
消防法における施設区分と指定数量の関係について、正しいものを選んでください。
1️⃣ 製造所では、取り扱う量にかかわらず指定数量の規定は適用されない
2️⃣ 指定数量未満であれば、どの施設も原則として許可不要である
3️⃣ 指定数量を超えて危険物を取り扱う場合、施設によっては許可が必要となる
4️⃣ 指定数量は取扱所だけに適用される基準である
📌 問題28【応用・実戦】屋内貯蔵所での保管手続きの判断
次のケースでは、どのような手続きが必要でしょう?
【条件】ガソリン(指定数量:200L)を180L、屋内貯蔵所で保管したい
1️⃣ 手続きは不要(無届で可)
2️⃣ 許可申請が必要
3️⃣ 届出が必要となる
4️⃣ 消防署の口頭指導のみで可
標識と防火設備の基礎知識|設置義務や表示内容を正しく理解しよう
危険物の取り扱いにおいて、標識の設置や防火設備の整備は欠かせない要素です。
本試験でも「どの施設に標識が必要か」「ラベルに何を記載すべきか」など、基本でありながら取りこぼしやすい内容がよく問われます。
ここでは、乙4法令模擬試験を想定し、実際の出題傾向に沿った重要ポイントを5問にまとめました。
この章の目次
📌 問題29:【過去問レベル】危険物標識の設置が義務づけられている施設は?
次のうち、危険物標識の設置が法律で義務づけられているのはどれでしょうか?
1️⃣ 一般住宅
2️⃣ 危険物の貯蔵所
3️⃣ 公園内の倉庫
4️⃣ 飲食店の厨房
📌 問題30:【過去問レベル】標識に記載すべき内容とは?
危険物施設に設置する標識には、次のうちどの情報を記載する必要があるでしょうか?
1️⃣ 製品のブランド名
2️⃣ 危険物の品名・数量・類別
3️⃣ 施設の建設年月日
4️⃣ 管理責任者の連絡先
📌 問題31:【応用・実戦】防火シャッターの設置対象はどのような施設か?
防火シャッターの設置義務に関連する施設として、最も適切なものはどれか?
1️⃣ 指定数量未満のガソリンを保管している屋内取扱所(防火区画あり)
2️⃣ 指定数量以上の第1石油類を常時取り扱う屋内貯蔵所(防火区画なし)
3️⃣ 指定数量未満の灯油を保管する屋外タンク貯蔵所
4️⃣ アルコール類を扱うコンビニ内の簡易倉庫(構造基準未満)
📌 問題32:【応用・実戦】標識の表示ミスが判明した場合の正しい対応は?
危険物貯蔵所に設置された標識に「品名」誤記があった。正しい対応として最も適切なのはどれか?
1️⃣ 誤記部分を消しテープなどで修正すれば対応完了
2️⃣ 標識を速やかに訂正し、必要に応じて消防署へ報告する
3️⃣ 外部から見えなければ問題ないため、掲示は撤去しても構わない
4️⃣ 点検記録に誤記を記録しておけば報告義務は生じない
📌 問題33:【基礎確認】ラベル表示義務の対象となる場面は?
次のうち、ラベル表示が義務づけられているケースとして正しいものはどれでしょうか?
1️⃣ 家庭でストーブ用に使用する灯油
2️⃣ 危険物を容器に入れて譲渡する場合(指定数量以上)
3️⃣ 倉庫内に表示があるため、容器は無表示でよい
4️⃣ 危険物を自社内でのみ使用する場合
保安監督者と責任者の役割|試験で問われる実務知識を整理
危険物取扱者試験では、単に資格を持つだけでなく、保安監督者や責任者としての役割と義務についても理解しておく必要があります。
とくに乙4試験では、実務に即した出題が増えており、「選任義務の有無」「責任範囲の違い」などが問われる傾向です。
このパートでは、よくある混同ポイントを中心に、模擬問題5問でしっかり確認していきましょう。
この章の目次
📌 問題34【基礎確認】危険物取扱者の定義に最も近いものは?
次のうち、「危険物取扱者」の定義として最も正しいものはどれでしょうか?
1️⃣ 危険物の販売に関する許可を持つ人
2️⃣ 危険物の設計と製造を担う技術者
3️⃣ 危険物の貯蔵・取り扱いに関する資格を持つ者
4️⃣ 危険物輸送を行う車両運転者
📌 問題35【過去問レベル】保安監督者が行う業務内容とは?
保安監督者の主な業務として正しいものはどれですか?
1️⃣ 危険物運搬時の交通指導を行う
2️⃣ 消防法に基づく設備設置の許可申請を行う
3️⃣ 危険物取扱者の資格取得手続きを代行する
4️⃣ 危険物施設の点検や保安業務の監督を行う
📌 問題36【過去問レベル】保安監督者の選任が義務づけられている施設は?
次のうち、保安監督者を必ず選任しなければならない施設として正しいものはどれですか?
1️⃣ 少量危険物のみを一時的に取り扱う仮設倉庫
2️⃣ 指定数量の1/5未満の危険物を保管する一般住宅
3️⃣ 指定数量以上の危険物を取り扱う製造所や屋内タンク貯蔵所
4️⃣ 災害時のみに稼働する避難施設内の非常用燃料置き場
📌 問題37【基礎確認】取扱者と保安監督者の資格要件の違いは?
危険物取扱者と保安監督者の違いについて、資格要件に関する説明として正しいものを選びましょう。
1️⃣ どちらも丙種資格で問題ない
2️⃣ 保安監督者は甲種限定で、取扱者は資格不要
3️⃣ 取扱者は資格が不要だが、監督者は必要
4️⃣ 保安監督者には乙種以上の資格と実務経験が必要
📌 問題38【応用・実戦】保安監督者と施設管理者の責任の違いは?
保安監督者と施設管理者の責任分担について、最も適切なものはどれですか?
1️⃣ 管理者は全責任を負うが、保安監督者は指示に従えばよい
2️⃣ 保安監督者は管理者を監査する立場にある
3️⃣ 保安監督者は現場の保安業務を担い、管理者は組織全体の安全管理責任を持つ
4️⃣ 両者の役割に違いはなく、業務は同等とされる
罰則と違反事例|試験で狙われるポイントを押さえる
危険物を取り扱う現場では、安全確保と法令順守が欠かせません。
万が一、法令違反があった場合には、思わぬ罰則が科されることもあります。
乙種第4類(乙4)では、こうした違反事例や責任の所在に関する出題も頻出です。
ここでは、罰則の基本から過去の事例を踏まえた応用問題まで、全4問で解説していきます。
この章の目次
📌 問題39【過去問レベル】無届保管に適用される罰則内容は?
次のうち、指定数量以上の危険物を許可・届出なしで保管した場合に科される罰則として正しいものはどれでしょうか?
1️⃣ 懲役1年以下または罰金100万円以下
2️⃣ 懲役5年以下または罰金300万円以下
3️⃣ 行政指導にとどまる
4️⃣ 警告文が届くだけで罰則はない
📌 問題40【過去問レベル】虚偽報告による処罰はどうなる?
次のうち、消防機関に対する報告として「虚偽報告」と見なされる行為はどれですか?
1️⃣ 実際より少ない保管量を申告した
2️⃣ ラベルの色合いを明るく加工した
3️⃣ 氏名の漢字を誤って届けた
4️⃣ 使用予定日を1日早く入力した
📌 問題41【応用・実戦】保安監督者を選任していない場合の責任者は誰?
次のケースで、法的責任を最も重く問われる可能性が高いのは誰でしょうか?
「指定数量以上の危険物を保管している施設で、保安監督者の選任がされていなかった。」
1️⃣ 現場の作業員
2️⃣ 危険物取扱者の資格を持つ社員
3️⃣ 法人の代表者または施設の管理者
4️⃣ 消防署の検査担当者
📌 問題42【応用・実戦】過去の違反事例から読み取れる教訓は?
過去に起きた危険物関連の事故や違反から、現場での安全管理において最も重視すべき姿勢はどれでしょうか?
1️⃣ 許可を取っていれば運用は自由に行ってよい
2️⃣ 点検よりもコスト削減を優先する
3️⃣ 手続きだけでなく実際の運用を重視する
4️⃣ 指導が来るまでは特に対応はしなくてもよい
法令条文と過去問対策|頻出条文を徹底対策
乙種第4類(通称「乙4」)の法令問題では、単なる暗記ではなく「内容の理解」が問われます。
特に消防法第9条〜第16条にかけては、毎年のように出題される重要条文です。
この章では、乙4法令模擬試験でも狙われやすい条文知識を、過去問レベルの出題形式で確認していきます。
この章の目次
📌 問題43【過去問レベル】消防法第9条の3の内容として正しいものは?
消防法第9条の3の規定内容として、正しいものはどれですか?
1️⃣ 危険物運搬に必要な車両表示の規定
2️⃣ 危険物施設の点検周期に関する事項
3️⃣ 製造所等の変更に伴う届出義務
4️⃣ 危険物を取り扱う資格者の定義
📌 問題44【過去問レベル】第10条で規定されている内容は?
次のうち、消防法第10条における規定として正しいものはどれですか?
1️⃣ 危険物施設の廃止手続き
2️⃣ 危険物の取扱いにおける火災予防措置
3️⃣ 危険物の保管数量の制限
4️⃣ 消防設備士の職務内容
📌 問題45【過去問レベル】第11条の施設設置基準とは?
消防法第11条で定められている施設に関する基準内容として、適切なものはどれですか?
1️⃣ 保安監督者の選任手続き
2️⃣ 危険物施設の技術的構造基準
3️⃣ 危険物取扱者の免状交付条件
4️⃣ 危険物の運搬経路に関する規定
📌 問題46【過去問レベル】第16条に基づく運搬義務とは?
消防法第16条で定められた「運搬時の義務」として、正しいものを選びましょう。
1️⃣ 危険物を積載中は消防署に連絡が必要
2️⃣ 運搬車両には標識や運搬書の携行が義務
3️⃣ 運搬する危険物の種類により資格が変わる
4️⃣ 危険物運搬時は交通ルールに従わなくてもよい
📌 問題47【過去問レベル】第14条の保安監督者の責務とは?
消防法第14条に基づき、保安監督者が行うべき業務内容として正しいものはどれでしょうか?
1️⃣ 危険物施設の保安業務を監督・指導すること
2️⃣ 危険物の販売に関する経理業務を行うこと
3️⃣ 法律改正の際に、従業員に通知すること
4️⃣ 消防署の指示に従い、現場で応援活動を行うこと
📌 問題48【応用・実戦】法令問題で問われる読解のポイントは?
乙4法令模擬試験において、法令問題を正しく解くために最も重要な視点はどれでしょうか?
1️⃣ 語尾の言い回しだけで判断する
2️⃣ 似た単語が並ぶ選択肢は全て正解とみなす
3️⃣ 条文の数字・条件・施設名の意味を正確に読み取る
4️⃣ 難しければ勘で早めに飛ばす
総合・応用問題|複数の知識を組み合わせて実践力をチェック
このパートでは、これまで学んできた内容をもとに、実際の現場に近い設定の中で複数の知識を組み合わせて解く応用問題を掲載しています。
「施設の分類」「標識の設置」「届出の要否」など、乙4試験で特に狙われやすい複合テーマが中心です。
選択肢の細かい表現にも注意しながら、読み取りの力を試してみてください。
📌 問題49【応用・実戦】施設分類・標識・届出の複合事例を問う
次の事例において、適切な対応として正しいものはどれですか?
ある工場では、屋内タンク貯蔵所を使用して軽油を1,500L、ガソリンを250L保管しています。 施設入口には標識が掲示されているものの、届出や許可申請はまだ行っていません。
1️⃣ 標識があるため、届出の必要はない
2️⃣ 指定数量を超えているため、届出が必要となる
3️⃣ 保安標識が設置されていれば法令違反には当たらない
4️⃣ 軽油とガソリンは別扱いのため、手続きは不要
📌 問題50【応用・実戦】運搬義務と選任義務を含む実践問題
以下の状況について、法令上の対応として不適切なものはどれでしょうか?
ある企業では、乙4の資格を持たない従業員が軽油1,200Lを運搬しています。 運搬に必要な書類と車両への表示はきちんと整備されていますが、保管施設には保安監督者が未選任です。
1️⃣ 危険物の運搬に資格者が必要とは限らない
2️⃣ 書類と表示が整っていれば運搬は合法
3️⃣ 保安監督者が選任されていない点は法令違反となる
4️⃣ 軽油は第4類なので監督者の選任は不要である
まとめ|乙4法令模擬試験で合格ラインを見極めよう
乙4危険物取扱者試験では、法令分野で15問中9問以上の正解(6割)が合格の条件です。
今回の乙4法令模擬試験は、実戦さながらの構成で50問に挑戦していただきました。
もし30問以上の正解が取れていれば、本番でも十分に戦える手応えがあるはずです。
「うろ覚えだったかも…」「似た選択肢でつまずいた…」という問題、ありましたよね?
そう感じたところこそ、あなたの伸びしろです。
では、ここで今回の要点をギュッと整理しておきましょう。
今回の要点
- 指定数量と手続きの関係(1倍超=届出、10倍超=許可)を正確に把握する
- 施設の分類(製造所・貯蔵所・取扱所)と、それぞれの特徴を区別できるようにする
- 条文の数字・条件・施設名は、丸暗記よりも使いどころをイメージして覚えるのが効果的
法令分野はとっつきにくく感じるかもしれませんが、パターンに慣れれば得点源に変わります。
これからも、無料で使える独学向けの教材を活用して、苦手を減らしながら着実に力をつけていきましょう。
次は過去問や分野別トレーニングで、さらに実力を固めていくのがおすすめです!

よし、なんとか30問超えた! 模擬試験って言っても、本番レベルだったな〜…
よく頑張ったね。でも、まだ“数字の落とし穴”に引っかかってたよ。法令は意外と“読む力”も試されるからね


うっ…たしかに…。でも次はちょっと気分変えて、もうちょい理科っぽいところやりたい
じゃあ次は“火が燃える条件”とか“燃焼の仕組み”を整理していこう。乙4の土台になる知識だから、ここを理解すると一気にラクになるよ

※本記事の内容は、2025年4月現在の情報に基づいています。制度や日程などは変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。